「歌手に向いてる人」とは?必要なマインド・スキル・行動を完全ガイド

「歌手になりたい」——この想いを胸に抱いたことのある人は多いでしょう。
憧れのステージ、スポットライト、歓声。誰かの心を震わせる歌声。そういった夢のような世界に、自分も立ってみたいと思うのは自然な感情です。
ですが、現実はどうでしょうか。
音楽が好きなだけでは足りない。歌がうまいだけでも難しい。プロの歌手として活動するためには、明確な「適性」や「準備」、そして「行動」が求められます。
私はこれまで音楽業界で30年近く携わってきましたが、印象的だったのは「天才じゃなくても歌手になれた人」の共通点です。むしろ「ある3つの力」がある人ほど、現実の壁を越えていく姿を数多く見てきました。
以前、歌手になるために理解しておきたい根本!2つのキーワードとは? というコラムで、「価値と根拠が必要」だという総論的な記事を書きました。
今回は、「歌手に向いている人の特徴」から「必要なスキル」「行動ステップ」「デビューの実態」まで、あらゆる疑問に答えていきます。歌手になりたいと思っているあなたが、「夢」から「実現」に向かうための現実的かつ前向きなナビゲーションになるでしょう。
- 歌手になりたいけれど、自分に向いているか不安な初心者〜未経験者
- オーディションやSNSなど、何から始めていいか迷っている10〜30代の男女
歌手に向いている人の特徴とは?

「自分って、歌手に向いてるのかな?」と感じる人は多いでしょう。ここでは、プロの現場で実際に活躍している人たちに共通する“本質的な資質”に焦点を当てます。歌が上手いだけでは足りない。
続けていく中で浮き彫りになる「想い」「姿勢」「楽しむ力」こそが重要なのです。あなたの中に眠る“向いている証拠”を、一緒に掘り起こしてみましょう。
音楽を愛し、自分を表現したいという強い想いがある
「なんで歌を歌いたいんだろう?」——この問いに、あなただけの言葉で即答できますか?
実は、プロの現場で輝いている歌手ほど、「自分にとって音楽が何なのか」を語れる人ばかりです。
売れるため、目立ちたいから、ではなく、「歌うことで誰かの心に触れたい」「生きた証を残したい」「自分の想いを音で表現したい」という強烈な“動機”を持っています。
ある女性ボーカリスト志望の子は、10代で両親を亡くし、音楽だけが心の支えだったそうです。「歌っているときだけ、自分をちゃんと肯定できるんです」と語ってくれました。彼女は今、メジャーアーティストのコーラス隊として全国ツアーに参加しています。
つまり、音楽との向き合い方が表現力の深さを生むのです。
あなたの中に、「この想いだけは歌で伝えたい」という感情はありますか?
人前に立つことを楽しめる自己肯定感と度胸
どんなに歌が上手くても、「見られること」に慣れていなければステージでは力を発揮できません。
逆に多少ミスしても、堂々としている人の方が魅力的に映ることもあります。
かつて歌手オーディションで、音程を外したのに会場を沸かせた女性がいました。理由は明白——目が輝いていたからです。リズムを体全体で感じ、オーディエンスとの空気を楽しんでいた。結果、彼女は審査員全員一致で二次審査通過。「あの度胸は、もはや才能」と言わしめたほどです。
歌手は、自分を魅せることを恐れない人が有利。
とはいえ、「人前が苦手だけど歌手になりたい」という人も、自己肯定感は後から育てられます。
最初は小さな発信でOK。自撮りでも弾き語りでもいい。誰か一人でも「いいね」と言ってくれた瞬間、その経験が度胸へと変わります。
挫折を乗り越えられるメンタルと継続力
「うまくいかない」「誰にも見られない」「思ったより反応が薄い」——これらは誰しもが通る道です。
実際、プロの歌手の多くが「やめようと思った瞬間」を経験しています。
でも、彼らがやめなかったのは、“結果”ではなく“音楽と関わる時間”に価値を見出していたから。
私の知人に、20代で5回オーディションに落ちた末、30歳でデビューした男性がいます。彼の口癖は「歌ってる時間が一番生きてる気がする」。不器用でも、細く長く歌い続けたことが、結果的に本物の魅力を育てました。
続けることは、それ自体が才能です。
そして、折れそうになったときこそ、自分の“なぜ歌うのか”を思い出してみてください。
歌手を目指すうえでのマインドセット
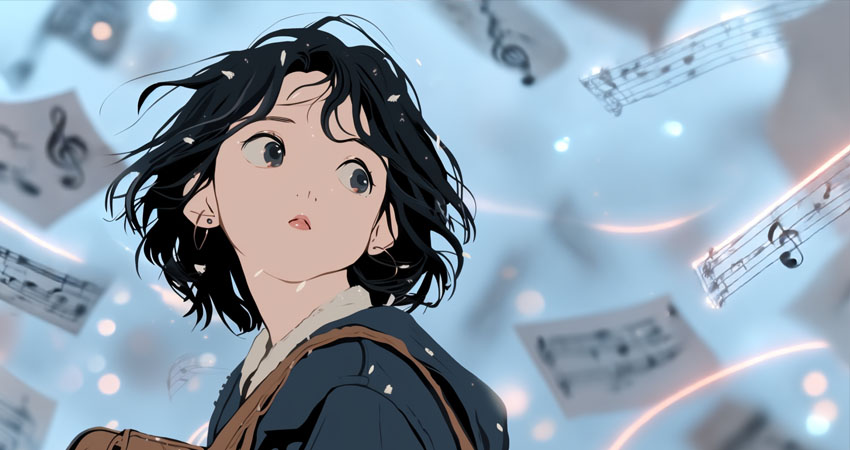
テクニックや努力ももちろん大切ですが、歌手を目指すうえで“マインドの持ち方”は何よりも基盤になります。夢と現実のギャップに押しつぶされないために、どんな視点で道のりを見つめるべきか。自分らしさをどう育て、どう保つのか——。プロを目指すからこそ必要な「心のスタンス」を、現場でのリアルな例とともに解説します。
「夢」から「目標」へ変える覚悟と現実感
「夢は歌手です」と語る人は多いのに、実際に行動する人はごくわずか。
その違いは、“夢”のままにしておくか、“目標”として落とし込めているか、です。
夢はふわふわしていて心地よい反面、現実の壁と向き合う必要がありません。
でも、目標に変わった瞬間、期限・方法・努力量・検証など、具体的なアクションが必要になります。
私が以前関わったある高校生は、「歌手になりたい」と言っていましたが、最初はただ好きな曲を歌ってSNSに投稿する程度。そこに「半年以内にオーディションに3件応募する」という目標を設定してから、一気に変わりました。
毎週ボイトレを受け、結果として実力も大幅に向上。実際、半年後には1次審査を突破しています。
「夢を目標に変える」——この覚悟が、最初のターニングポイントです。
比較ではなく「自分の魅力」にフォーカスする視点
SNSやオーディションでは、必ず“他の誰か”の歌に出会います。そして、ほとんどの人がこう思うのです。
「この人のほうが上手い」「声質が魅力的」「自分には足りない」
でも、それは当然のこと。音楽は多様性の世界であり、比べて優劣をつけるものではありません。
むしろ、プロとしてやっていく上では「自分にしかない魅力」があるかどうかが重要です。
声のトーン、音の抜け方、言葉のニュアンス、ステージでの表情。それらの個性が誰かの心に刺さります。
たとえば、ある女性アーティストは「音域も狭く、リズム感も普通」でしたが、「言葉の運び方が天才的」と評されメジャーデビューを果たしました。
彼女は「私は上手いじゃなくて、刺さる歌を歌いたい」と言い切ります。
あなたは、誰と比べるために歌っていますか?
それとも、「誰かの心に届けたい」ために歌っていますか?
成功に固執せず「音楽と向き合い続ける姿勢」
音楽の世界は、思った以上に「報われないこと」の連続です。
どれだけ努力しても結果が出ない日もあるし、誰にも気づかれない日々が続くこともあります。
でも、だからこそ問われるのは「どこまで音楽を愛せるか」。
一過性のブームやフォロワー数に一喜一憂せず、ただ純粋に歌と向き合い続けることができるか。
ある先輩ミュージシャンは、売れない時代に「10人の前でも、1000人の前でも、同じように歌える自分でいたい」と話していました。
そのブレなさが、ファンとの信頼を育み、結果として長く愛される存在となったのです。
「歌手になる」とは、成功の結果だけを目指すことではありません。
歌うことそのものを“自分の人生”として引き受ける覚悟——それが最も大事なマインドセットです。
歌手になるためのスキルと準備

「何を準備すれば歌手になれるの?」という疑問に答えるこの章では、歌唱力・表現力・自己プロデュース力まで、多角的に解説していきます。単に“歌がうまい”では通用しない時代だからこそ、基礎+個性+発信力をバランスよく育てることが求められます。歌を武器にするための「実践的スキルと準備」をここで整理しましょう。
ボイストレーニングで基礎力を身につける
歌手を目指すなら、やはり避けて通れないのが「発声技術」です。
生まれつきの声質や音感ももちろん影響しますが、正しい発声を習得することで声の響き方やスタミナは劇的に変わります。
実際、私が運営するレッスンスタジオでは「ボイトレを始めて3ヶ月で音程のブレが激減」「半年で高音域が安定した」といった例が多数あります。
では、なぜ独学では限界があるのか?
一番の理由は「自分の声を客観視できない」ことです。声の出し方、喉の使い方、ブレスの位置、どれも他人の指摘がないと気づきづらい。だからこそ、プロによるフィードバックを受けることが効率的なのです。
カリスマ美容師だって自分頭は切れないように、必ずセコンドが必要なのです。
さらに重要なのは、「歌う筋肉を鍛える」という視点。声帯、腹筋、横隔膜の連携は、継続的なトレーニングによって初めて本領を発揮します。スポーツと同じですね。
基礎が整うと、表現力に集中できるようになります。
それが「伝わる歌」への第一歩なのです。
表現力・リズム感・ステージ経験を積む方法
歌は、ただ音をなぞるだけでは成立しません。
「声と言葉にどんな感情を込めるか」が聴く人の心を動かします。
表現力は、演技力とも通じます。歌詞の意味を深く理解し、自分の経験と照らし合わせることで“嘘のない声”が出せるようになります。
あるシンガー志望の若者は、「恋愛経験が乏しいからラブソングがうまく歌えない」と悩んでいました。でも、別に恋人じゃなくてもいいのです。大切な人を思う気持ち、失いたくない何か……そういった感情の核にアクセスすることが表現の原点です。
そしてリズム感。
音楽ジャンルによって求められるノリや間の取り方は異なります。これはカラオケで養うのは物理的に無理なので、ボイトレをしましょう。
ステージ経験は、度胸とパフォーマンス力の両方を育てます。
最初は小さなライブハウス、路上ライブ、学園祭でOK。とにかく「観客の前で歌う」ことが最大の練習になります。
楽曲理解力・作詞作曲・セルフプロデュースの基礎
現代の歌手には「ただ歌うだけ」ではなく、クリエイター的視点が求められる場面が増えています。
特にSNS時代では、自己プロデュースの力が注目の差を生みます。
たとえば、作詞や作曲にチャレンジすることは、自分の音楽性や言葉のクセを客観視する大きなきっかけになります。曲づくりができれば、自分の歌の魅力を最大限に引き出すオリジナル曲を手にすることができます。
また、最近ではDAW(音楽制作ソフト)を使って自宅で簡単に楽曲を作れる時代。基本のコード進行、打ち込みの仕組み、録音・MIXの知識があれば、セルフプロデュースの幅が一気に広がります。
さらに、自分の世界観を統一して伝える工夫も重要です。
SNS投稿、衣装、アートワーク、MVのコンセプト……全てが「この人はどんな歌手か」を表現するパーツとなります。
歌うことに加えて、創る力と届ける力を育てていきましょう。
歌手になるための行動ステップ
スキルやマインドを整えても、「どう動けばいいのか」がわからなければ前に進めません。この章では、初心者が最初に踏み出すべき3つのルート——オーディション・SNS発信・ライブ出演などについて具体的に紹介します。「いきなりプロ」ではなく、「今日からできること」に着目した現実的な行動指針をお届けします。
オーディションへの応募と選び方
プロの歌手になるための最も王道なルートのひとつが歌手を発掘するオーディションです。
とはいえ、ただ応募すればいいというわけではありません。重要なのは、どんなオーディションを選ぶかです。
まず大前提として、自分の音楽ジャンルや方向性に合った主催者を選ぶこと。J-POP志向なのにアニソン特化のオーディションに出ても、評価されにくい可能性があります。
また、オーディションには「事務所所属型」と「メディア出演型」「アーティスト発掘型」など様々なタイプがあります。
たとえば、音楽事務所主催のオーディションは、合格後にマネジメントやボイトレ支援が受けられる代わりに、契約内容をよく確認する必要があります。
逆にテレビやWEB系のオーディションは話題性はあるものの、その後の活動は自分次第。
応募前には以下を確認しておきましょう。
- 審査基準とジャンル傾向
- 応募後のサポート体制(契約内容、レッスンの有無)
- 過去の合格者の活動実績
「応募すること=チャレンジ」ではありますが、何にチャレンジするのかは見極めが必要。
自分の価値を活かせる場を選ぶことが合格への近道です。
YouTubeやSNSでのセルフ発信の始め方
現代の音楽シーンでは、「SNSからの発見」がプロデビューに繋がることも珍しくありません。
実際にTikTokやYouTube発のシンガーが、レコード会社から声をかけられるケースは急増しています。
では、どこから始めればいいか?
まずは、自分の歌を録音・録画し、スマホで簡単に編集するところからで十分。
映像美や編集技術よりも、「この声いいな」「この人の歌、心地いい」と思わせる音の力が重要です。
投稿する内容の例としては——
- カバー曲(自分の世界観に合ったものを選ぶ)
- ワンフレーズ歌唱(15秒〜60秒の短尺が特に有効)
- 自作曲やフリースタイル
- 日常+歌(親近感を与える工夫)
特にYouTubeはアーカイブ性が高く、積み上げが評価に繋がります。一方、TikTokやInstagramは拡散力があり、バズれば一気に注目を集められます。
どちらか一方に絞る必要はありません。
「あなたの声を、知らない誰かに届ける」——それが発信の本質です。
ライブ出演や専門学校など実践的な活動の場を持つ
実際の現場に出ることは、技術以上に「人間としての深み」を磨いてくれます。
どんなにボイトレや発信をしていても、“生身の体験”がないと、歌は平坦になってしまうものです。
たとえば、地域の音楽イベント、カフェでのアコースティックライブ、オープンマイク。最初は観客が3人でも構いません。
「目の前の誰かが自分の声を聴いてくれている」——この感覚は、動画投稿だけでは味わえない、特別なものです。
また、音楽系の専門学校や養成所に通うことも一つの手段です。
体系的なスキルが身につくだけでなく、同じ志を持つ仲間と切磋琢磨することで、自分の限界を超える原動力になります。
最近では、週1から通える社会人向けの音楽スクールも増えています。
私の運営するアーティスト育成機関でも、「会社勤めしながら月2回通っていた生徒」が、1年後には自主企画ライブを成功させ、レーベルから声がかかった事例があります。
大切なのは、「待つ」のではなく「動く」こと。
ステージは、与えられるものではなく、自分で作る時代です。
芸能事務所への所属・デビューの現実

「芸能事務所に入ればすぐデビュー?」そんな誤解を持つ人も少なくありません。ここでは、事務所所属のリアルな仕組みや契約時の注意点、さらには“自分に合った活動スタイル”の選び方まで詳しく解説します。チャンスを掴むには、現実を知り、正しく判断する目が必要です。プロの世界の入り口を、冷静かつ前向きに見つめてみましょう。
芸能事務所に所属するための準備と心構え
「芸能事務所に入ればデビューできる」と思っていませんか?
実のところ、事務所所属=即プロ活動、というわけではありません
まず知っておきたいのは、芸能事務所には「即戦力として売り出す人」と「育成枠で様子を見る人」の2タイプの契約があるということです。
前者はすぐに仕事が与えられますが、後者は数年にわたってレッスンや自己研鑽を求められることもあります。
また、どの事務所に所属するかによって、将来の方向性が大きく左右されます。
たとえば、アイドル系に強い事務所と、アーティスト志向の事務所では育成方針も、営業スタイルもまるで違います。
準備として必要なのは、以下の3つ。
- 歌唱力・表現力といった技術の向上(オーディションでの評価対象)
- 自己PRの明確化(自分の強み・方向性を言語化する)
- SNSやライブなど“活動実績”の可視化(すでに動いている人が好まれる)
「選ばれる」のではなく、「選びに行く」視点も持ちましょう。
事務所に入ること自体がゴールではありません。むしろ、そこがスタートラインです。
デビューのタイミングとよくある誤解
「いつかきっとデビューできる」——そう信じて活動している人も多いですが、
実は「デビューの定義」が人によって曖昧だったりします。
CDリリース?配信開始?事務所契約?メディア出演?
実際には、明確な線引きは存在せず、自主制作でも配信でも「歌手として活動していれば、それはすでにデビュー」とも言えるのです。
つまり、「デビューを待つ」のではなく、「自らデビューする」時代なのです。
もちろん、事務所やレーベルを通した“商業的デビュー”を目指すなら、企画・タイミング・パートナー選びが非常に重要です。
ただし、準備が整っていない状態でデビューしてしまうと、リスナーや業界に“低い完成度の印象”を残すリスクもあるため注意が必要。
音源のクオリティ、パフォーマンス、アーティストイメージ
これらをしっかり練り上げたうえで、「ここで出すべきだ」と判断するタイミングを見極めましょう。
事務所との相性や契約内容を見極める視点
華やかなイメージの裏に、契約トラブルのリスクがあるのもこの世界の現実です。
中には「退所後に楽曲使用禁止」「活動制限がかかる」といったケースも実際にあります。
それは事務所の立場からすると、事務所自身や他の所属アーティストを守るために敷くルール。だからこそ皆さんは、事務所と契約する際は以下の点をしっかり確認しましょう。
- 活動エリア・ジャンル・育成スタイル(自分と合っているか)
- 契約期間と更新条件(辞めたくなった時にスムーズか)
- 権利関係(音源の著作権、映像・SNSアカウントの管理など)
- レッスン・活動費用の有無(実費負担がないか)
根本的に「レッスン費は無償前提だという価値観」の方は、今すぐ夢は諦めてください。あなたのために、あなたに代わってお金を出す人は皆無ですから。
なお、「所属したい」と思える事務所がない場合は、無理に契約せずフリーで活動し続けるという選択もありです。
実力と影響力がつけば、向こうから声がかかることも無くはありません。
[Q&A]よくある質問
- 未経験でも歌手になれますか?
- もちろん可能です。実際、プロの歌手でも「本格的に始めたのは20代から」という人はたくさんいます。
大切なのは、今の自分にできることから動き出すこと。経験は後から積めます。諦める理由にはなりません。 - 自分に才能があるかどうか不安です
-
誰もが最初は不安ですし、「才能があるか」はやってみないとわかりません。
むしろ、続けられる力こそが才能です。上手いかどうかより、「歌いたい」という想いを持ち続けられるかが未来を左右します。 - 「普通の人生」と迷っています。どうしたら?
-
「普通の人生」か「夢の道」か——二択に思えるかもしれませんが、実は両立している人も多くいます。
本業を持ちながら音楽活動を続けるのも立派な道。大切なのは「どんな形でも、音楽を諦めない」ことです。
- 歌手に向いているかどうかは「才能」ではなく「行動の中」で見えてくる
- “憧れ”を“現実”に変えるには、「今できること」を積み重ねるしかない
- プロになる道は一つじゃない。「あなたに合ったルート」を見つけることが第一歩
プロの歌手として活動するには、技術や経験はもちろん必要です。
しかしそれ以上に問われるのは、「音楽をどれだけ本気で愛しているか」「どんな逆風でも歌い続けられるか」——そんな姿勢の部分です。
誰かと比べる必要はありません。誰よりも自分らしくあること、そのために今日、声を出してみる。
1人でも多くの人に、自分の歌が届くように願いながら、少しずつ階段を登っていけばいいのです。
未来はまだ白紙です。
けれど、あなたが“今この瞬間”に踏み出した一歩は、確かにその白紙を塗り始めています。音楽をやめないあなたには、きっとチャンスが巡ってきます。
焦らなくていい、自分のペースで。でも、決して止まらないでください。
さあ、次はあなたの番です。その声を、世界に響かせていきましょう。
